藤原 正彦 国家の品格 新潮新書 [日記(2006)]
日本人にとって、まことに耳に快い理論が展開される。金で人の心が買えると豪語する経営者や、株式による企業支配と錬金術師が時代の寵児ともてはやされる現在の日本と国民に、「品格」を問う一冊。
著者は(世界的な)時代の閉塞感は西欧的論理(理論ではなく)と近代合理精神の破綻がもたらしたものだということから論を始める。そしてその対立概念として(なんと)武士道を置く。
第二章で、現代においてこの「論理」主義が通じなくなっていることを論じる。論理には限界があること、論理の出発点は非論理の仮説であること、曖昧さ含んだ論理を積み重ねてゆくと最後はとんでもない結論に行き着くことなどを実例をあげて述べる。
国際人を育てるという命題の論理的帰結が、小学生から英語教育をする愚(英会話より、話す中身の学習が先ではないの?)であり、生きた経済を学ぶ帰結が、にこれも小学生に株式投資を教える愚(マネーゲームと錯覚する投資家を育てるだけ)を著者は笑う。国際人→英語教育、経済の勉強→株式投資の図式は、著者が云う「論理」ではなく短絡であろう。新渡戸稲造は英語が出来たから国際人であったのではなく、武士道を英語で書いたから国際人になったのであり、英語は入れ物に過ぎない、要は中身。この著者の理屈は正しい。だから学ぶべきは武士道や古典である、のかどうか。
要はバランスの問題だと思うが。
次いで、自由、平等、民主主義が槍玉にあがる。ロック、アダム・スミス、ジェファーソンをこき下ろし、自由と民主主義の下では国民はヒットラーを生み出しかねない。だから国民を撫育する「真のエリート」が必要という図式にはならないだろうと思うが。民主主義や自由は「欧米が作り上げた『フィクション』」であるかどうか。論理と民主主義の対極に、著者は「武士道」を置く。美しい日本の四季のなかで、日本人は「もののあはれ」を感じる「情緒」を育み、弱者に対する「あはれ」を感じる「武士道」が生まれた。西洋の論理が息詰まった今、世界を救うのは武士道だ!分かるんですけど・・・。
規制緩和、市場主義も槍玉にあがる。著者によると、「グローバリズムの中心的イデオロギーである『市場経済』は、社会を少数の勝ち組と大多数の負け組にはっきり分ける仕組み」と規定される(ここで、ハリケーン被害のニューオーリンズの貧困層の事例が引かれる)。規制緩和と市場主義は昨今旗色が悪い。だから「二十一世紀はローカリズムの時代」ということになり、当然武士道に帰結する。
市場主義を、著者にように見えざる神の手に委ねる予定調和と見るのではなく、民主主義を最大多数の最大幸福による合成の誤謬ではなく、産出・結果(output)が投入・原因(input)に組み込まれ、生み出される歪みを最小限に押さえるシステムととらえてみてはどうだろうか。システムのメカニズムが円滑に動くエネルギーが自由と平等ではないかと。
今年の冬は灯油の価格が例年の2倍近くまで上昇した。原油の高騰がまわりまわって家庭まで及んだわけだが、なるべく灯油を使わない工夫、ガス等の代替エネルギーを使わないメカニズムが働き、市場主義のメカニズムは灯油の価格を押さえる方向に働いたはずである。とまあ、勝手なことを考えてしまう。
先日の新聞に新渡戸稲造の「武士道」の広告が載っていた。この本の最大の功績かもしれない。
お勧め度 →★★★☆☆



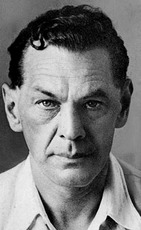



コメント 0